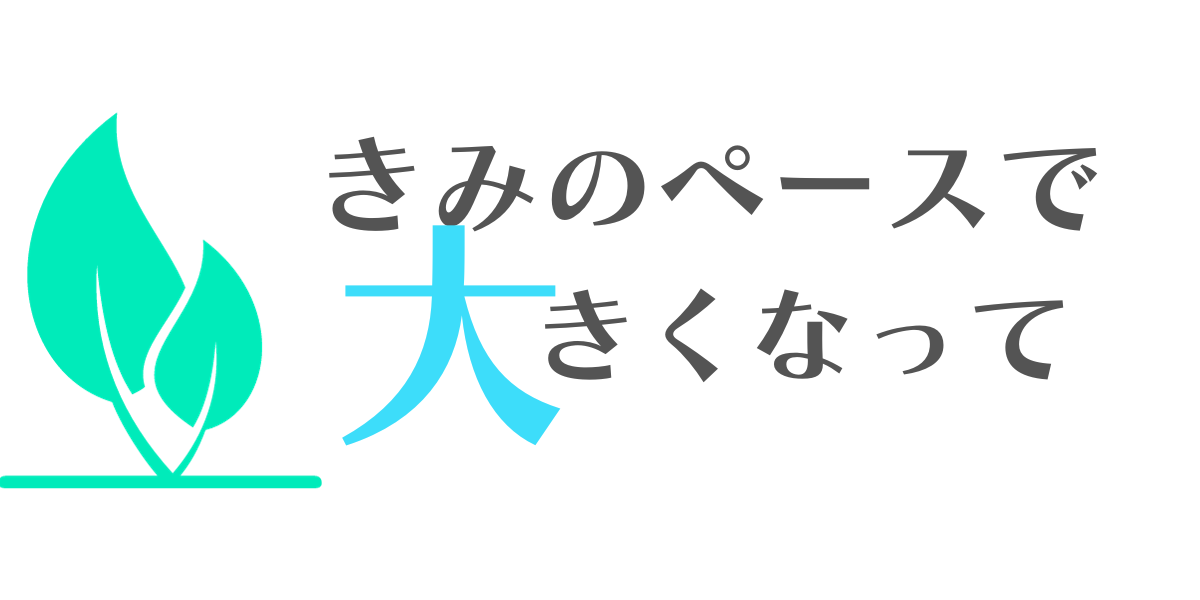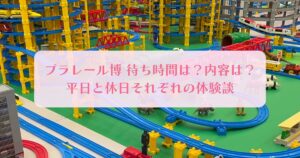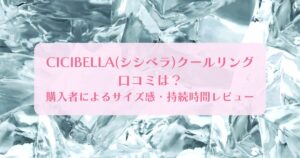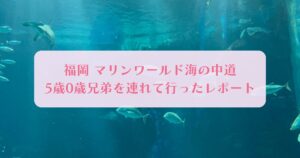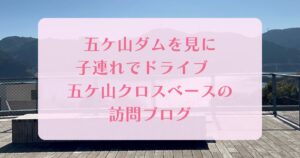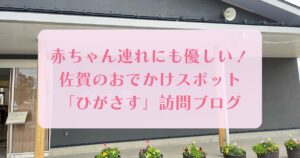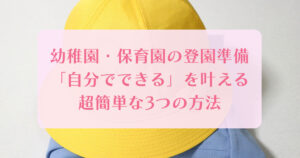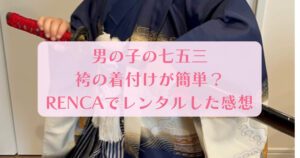お買い物ごっこをお家でしている!という方は多いと思います。
せっかく遊ぶのなら、一歩踏み込んで、お金のお勉強ができたらいいなと思いませんか?
『どうぶつ村のおかいものゲーム』では、すごろくゲームで遊びながらお金の勉強をすることができるんです。
実際に5歳の長男と一緒に遊んでみたので、その時の様子や良い点・気になる点をお伝えします!
概要
『どうぶつ村のおかいものゲーム』は学研プラスから発売されている子供向けのボードゲームです。
2つのすごろくゲームと8つのミニゲームが楽しめます。
ゲームは全て、「お金の学び」がかかわるものです。
メインの2つのすごろくゲームについて
どちらも、すごろくを通して、「おかいもの」をしてお金をやり取りしていきます。
ルールはサイコロを振って出た数だけコマを進め、所定の指示に従うというスタンダードものです。
2つのすごろくの主な違いは下記にあります。
- すごろく①はおかいものをするだけのシンプルなルール
- すごろく②は前半でお金を稼ぎ、後半でお買い物をする少し難易度の高いルール
「おかいもの」マスでお買い物体験
どちらのすごろくにも共通であるのが「おかいもの」です。
「おかいもの」マスでは、指示された「しょうひんカード」と「おかね」をプレイヤーとレジ係でやりとりして「おかいもの」をします。
写真のようにどこかにありそうでなさそうな「しょうひん」がたくさん用意してあり、ちょっと微笑ましくなります。
お金を稼ぐ体験も
すごろく②では、前半はお手伝いをしてお金を「稼ぐ」ことも学びます。
お手伝いの内容で金額が変わるので、いかに効率よく稼げるかで後半のお買い物のしやすさも変わってきます。
お買い物以外も楽しい!
ちゃんとすごろくとしても楽しいです。
マスの指示には、すごろくでよくある「○マスすすむ/もどる」「一回やすみ」や、おかねをもらえるチャンスマス・お金を失ってしまうアンラッキーマスもあります。
すごろく②ではイベントマスも充実しています。
後ほど「しょうひん」がもらえる「ふくびきけん」をゲットしたり、「びんぼうカード」を引かされたりとなかなかスリルがあります。
すごろく以外にも充実したコンテンツ
他にも楽しめるミニゲームが8種類。お金の大小や種類、商品価値などを学ぶことができます。
さらに他の楽しみ方も…。
賑やかな盤面は、実はさがし絵遊びもできます。箱に見つけてほしい「お題」が描いてあります。
大きなすごろくシートを隅々まで眺めるのもなかなか楽しいです。
実際に5歳の息子と遊んでみた!感じた良い点4つと気になること
5歳の息子と一緒に、2つのすごろくを中心にやってみました。
難しいことを考える必要はあまりなく、運がほぼ全てのゲームなので、年齢での有利不利はありません。
良い点①:難易度調整がきちんとされていて長く遊べる
2つのすごろくの難易度が違うため、成長に合わせて長く遊べます。
簡単なルールのすごろく①は、登場するのは低額(300円くらいまで)の商品のみで、お金のやり取りは10円単位。
一方、すごろく②は高額な商品も出てきますし、1円単位でのやり取りが必要なので計算もやや複雑。また、イベントマスではちょっとした波乱が起こることもあり、大人でもヒートアップしてしまいます。
 とうこ
とうこ私は一度、びんぼうカードマスに止まりまくって、息子にボロ負けしました…。
良い点②:「買いたくても買えない」ことがあるのを学べる
ゲーム内で全て思った通りのものが手に入らないことを学べます。
例えばお金が足りないと、お買い物は成立しないルールです。「破産でゲームオーバー」ではなく、ゴールするまでは進めなければいけません。
このシステム、予算内で買い物するという大切なことを身につけるいい機会だなと思います。
よく、「〇〇買ってよ〜!!!」とぐずる子をスーパーで見ますね(うちの子もよくやっていました…)。その状況をゲームで体験でき、買えないことを実感してもらえます。
さらに、3人以上でゲームを進めると、しょうひんカードが各種2枚ずつしかないため、「売り切れ」が発生します。これも「買いたくても買えない」の一種ですね。
良い点③:通貨が「円」
使用する通貨が円なので、わかりやすいです。お金を身近に感じるきっかけになるでしょう。
商品価格については…ちょっと安めの値付けが多いかなとは思います。ゲームが物価上昇が始まる前に販売開始になったことと、やはり子供向けなのもあって…ただし、大きくズレてる感はないです。
良い点④:ほぼ全てのコイン・紙幣が網羅されている
ほぼ全ての硬貨・紙幣が網羅されていて、遊んでいるうちに自然と覚えられます。
すごろく①では使用するのは10円・50円・100円がメインです。すごろく②ではコイン全種類と1,000円札を使用します。さらにミニゲームまで含めると、2,000円札以外のお金は全種類扱うことになります。
特に、すごろく②は硬貨の種類がどうしても必要です。どんな種類の硬貨があるのか、どう組み合わせればいいか、ピッタリ払えないならいくら出しておつりをもらうかなどをしっかり考えないとゲーム中にもたつきがち。なので、否が応でも頑張って覚えてくれます。
ゲームで遊びながら、これらのことを考える練習になるのは良いなと思いました。
気になったこと:「お金」が扱いづらい
ゲームに欠かせない「お金」ですが、一度置いてしまうと拾い上げるのに苦労します。
「お金」は厚紙製で、大人でも持ちにくいです。不器用な長男は1枚手に取るだけでも数十秒かかっていました…





個人的にはこれがこのゲームの最大の弱点だと思います。
表示金額によっては「100円が4枚、10円が2枚…」というふうに、一度に数枚ずつやり取りすることもあるのでそこでゲームの流れが、いちいち中断してしまいます。
2回目からは、祖父母宅にあったお金のおもちゃをもらってきて使っていました。それでも、結構な枚数の硬貨を使うので、結局不足分は厚紙製のお金を使用することになります。
元々のゲームの購入価格からすると仕方がないのかもしれませんが…ちょっと残念な点でした。
気になったこと:3才には難しすぎる
対象年齢は3歳からとなっていますが、実際は4歳後半〜5歳くらいからという印象です。
ゲームを楽しむためには少なくとも下記ができていないと厳しいと思います。
- お金がどんなものかわかっている
- お買い物は何をするのか知っている
- 数字がある程度読める
個人差はあるでしょうが、3歳は結構厳しいでしょう。楽しく遊べるのは、年中〜年長さんくらいからかなと思います。
子供だけでは遊べないかも
お金のやり取りの部分があるので、子供だけで遊ぶことはなかなか難しいでしょう。
レジ係のお仕事は大人のサポートが必要かもしれません。少なくとも3桁以上の足し算引き算ができるか、電卓が使えないと難しいです。
さらに、勝敗の判定もお金や「しょうひん」の金額を計算しなければいけません。総合的に、7歳でできるかできないかくらいのレベルでしょう。
その分、親子で遊ぶのにはぴったりです。
おすすめしたい人
『どうぶつ村のおかいものゲーム』をおすすめしたいのは次のような人です。
- 親子で遊べるゲームを探している人
- 4〜5歳以上の子供と楽しみながらお金の教育をしたい人
- 長く遊べるすごろくゲームを探している人
- 一歩踏み込んだお買い物遊びをしたい人
『どうぶつ村のおかいものゲーム』は、すごろくゲームなどで楽しく遊びながら、お金の基礎を身につけることができるボードゲームです。対象年齢は3〜7歳となっていますが、実際はしっかり楽しめるのは4歳後半〜5歳くらいからかもしれません。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!