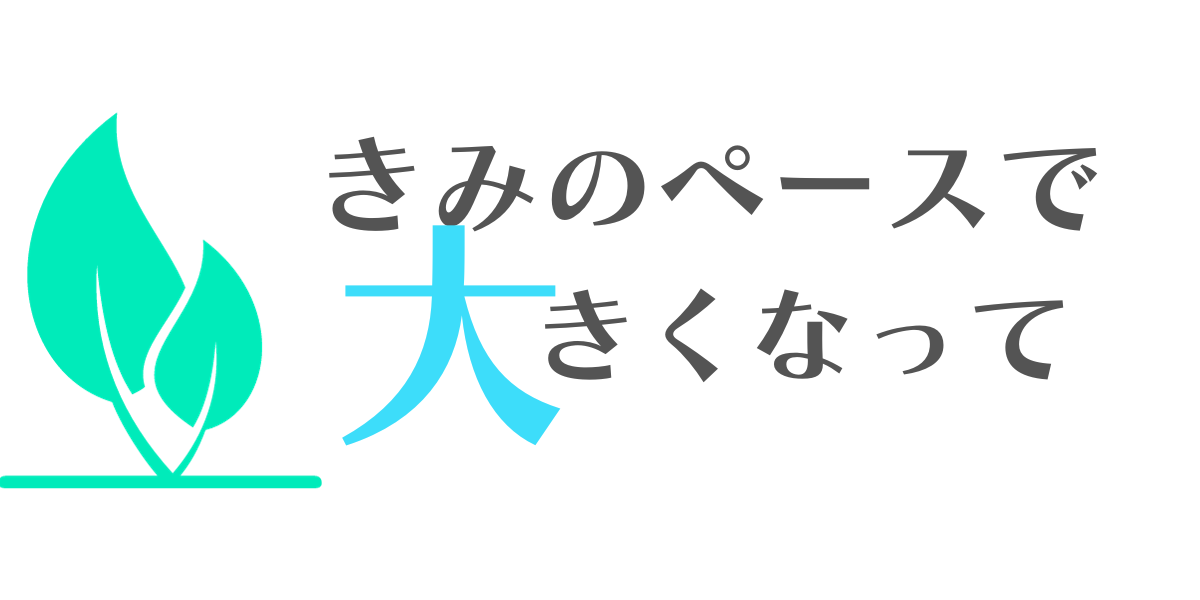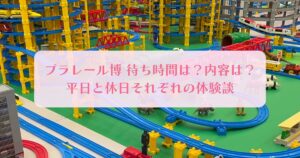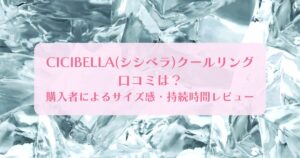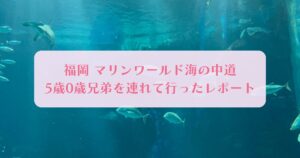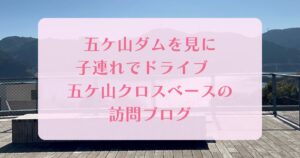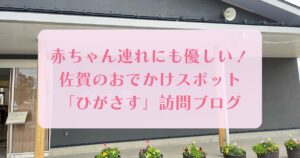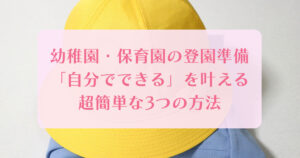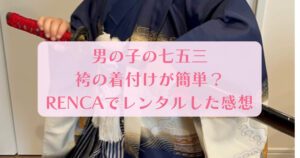「ひらがなのワークブックを買ってみたけど、子供が嫌がって手をつけない。」
「楽しみながらひらがなを覚えられる方法ってないのかな?」
長男が2才の後半になった頃、初めてひらがなのワークブックを買ってみました。が、1〜2ページは楽しそうにやるものの、すぐに飽きてしまいちっとも続きませんでした。
3才後半で大好きな電車のひらがなブックを買い、気が向いたらやっているものの1年以上たってもまだ終わらず…
しかし、そんな長男でも、年少さん終わりまでにはひらがなはほぼ全て読むことができ、自分の名前や簡単な文字は書けるようになっていました。
文部科学省の資料[1]をみると、年少の男の子でかな文字が読めるのは約6割、自分の名前をひらがなで書けるのは3割くらいとのこと。
 とうこ
とうこ必ずしも早くできるのが良いとは思わないけど、
そんなに悪くないかも!
我が家ではなるべく嫌がらない範囲で、ひらがなを教えていたのが良かったのかもしれません。
ただし、自己流で覚えさせてしまうと間違ったまま覚えてしまって小学校で辛い思いをする可能性もあります。どちらかというと、変な覚え方をしないようにということにはかなり気を使いました。
そこで、我が家でどのような取り組みをしたか、またどういうことに気をつけたかをお伝えします!
- ワークブック以外でひらがなの読み書きを覚える方法が知りたい
- お家でひらがなを教えるときの注意点を知りたい
楽しみながらひらがなを覚えられる取り組み5つ
長男は主に次の5つの遊びを通して、ひらがなを覚えていきました。
- ひらがなカードやパズル
- 絵本の音読
- かるた遊び
- お風呂ポスター
- お手紙
嫌々ながらやるよりも、楽しく遊ぶ中でひらがなを覚えられた方がいいですよね。
一つづつ、詳細をご紹介します。
ひらがなカードやパズルで遊ぶ
ひらがなが1枚に1文字書かれたカードやパズルで、自分の名前や好きな言葉の文字を探すのがおすすめです。バラバラにしてから「あいうえお」順に並べるのも良いでしょう。慣れてきたら、その場にあるカードから選んで単語を作っていくゲームも楽しいですよ。
我が家ではモンテッソーリ式の砂文字カードを買っていました。これは、文字がざらざらしていて、上からなぞってひらがなの書き方を覚えるのにも使えるものです。



うちの子はさっぱりなぞりませんでしたが。
好きなように遊べば良いのです。
絵本の音読をしてもらう
絵本の読み聞かせの時に、読みやすそうなところを指差して本人に読んでもらう方法です。最初はたどたどしいですが、次第にスムーズに読めるようになるでしょう。
お人形や下の子のお世話が大好きな子なら赤ちゃん向けの文字の少ない本を「読んであげてね」と渡すのも良いでしょう。
長男は読んでもらうのが大好きですが自分で読むのは苦痛なようでした。なので、本当に機嫌のいい時でないと一文字も読んでくれませんでした。ところが、弟が生まれた後は簡単な絵本を探してきて「ぼくがよんであげるね!」と読み聞かせ(らしきもの)をしてくれるようになりました。
かるたで遊ぶ
かるたは親を負かそうと全力で札を探すので、自然とひらがなを覚えてくれます。ある程度読めるようになったら、読み札係を任せても楽しめるでしょう。
市販のかるたには、ことわざ・慣用句を扱う定番の「犬棒かるた」以外にも、キャラクターや乗り物・動物を題材にしたものなどたくさんのバリエーションがあります。子供の興味関心に合わせて選んでみてください。
長男はこのことわざカルタがお気に入り。自然とことわざも覚えて、保育園の先生を驚かせていました。


お風呂ポスターを貼る
お風呂の壁に貼れるポスターも楽しみながら文字を覚えられるアイテムです。こちらも乗り物やキャラクターなど、子供の好きなものにあわせて選べるのが良いところ。
現在、長男はお風呂ポスターでカタカナを覚えていますが、みるみるうちに読めるようになってびっくりしました。小鉄の我が子はお風呂の度に電車ポスターを大喜びで壁に貼り付けています。
お手紙のやり取りをする
おじいちゃんおばあちゃん・お友達・先生など身近な人へのお手紙を書きたがったら、チャンスです。文面を一緒に作ると難しい文字でもみずから書いてくれるかもしれません。
我が子はワークブックは嫌がるのに、お手紙になるととても張り切っていました。
弟の出産時にママが入院したときは毎日祖父母と一緒に手紙を書いて持ってきてくれました。
ひらがなを覚えるときの注意点と対策方法
ひらがなを覚えるとき、次の3つのことができているか注意をしてください。
- 正しい姿勢で書く
- 正しい持ち方で書く
- 正しい筆順を覚える
実際に、早いうちから文字を覚えた子供は、書く姿勢や持ち方が正しく身についていなかったり、書き順がでたらめだったりすることが多いそうです[2, 3]。そうなると、小学校でもう一度、一から学び直さなければいけません。
お家でできる対策方法
せっかく覚えたことを無駄にしないために、お家でできる対策を調べたり考えたりしてみました。
声かけをする
文字を書くとき、姿勢・持ち方・筆順など、正しくできているかを見てあげてください。
我が家では姿勢や鉛筆の持ち方については一緒にyoutube動画で確認をしました。
幼児用の筆記具を選ぶ
小さな子供の手はまだ不器用。一般的な六角形や丸だと持ちにくく、細いと握り込んでしまうとのことです[2]。
そんな幼児でも持ちやすい、太めの三角形の鉛筆がちゃんとあります。
芯も、筆圧が低くてもしっかり書けるB6など濃いものです。
また、正しく持てるような補助具も販売されています。



なぜかわからないのですが…たまたま行ったコンビニで
公文式の幼児用鉛筆と補助具が売っているのを見つけて即買い!
以降ずっと愛用してます。


筆順がわかる教材を使う
あいうえお表などは筆順の番号が振ってある教材を選ぶのが良いでしょう。その時も、「数字の順番に書くんだよ」と声かけは必須です。
長男が(めずらしく)ワークを頑張っていたとき、振ってある番号を全く意識せずに書こうとしていたのを見て焦ったことがあります。ただ、一度「番号順に書けばいいんだ」とわかるとそのあとはちゃんとできるようになりました。
ワークブックができなくたってひらがなは身に付く!
集中力のもたない子でも、さまざまな遊びの中でひらがなを覚えることはできるでしょう。
我が家の長男は次のようなものを利用して、楽しみながら段々とひらがなの読み書きを覚えていきました。
- ひらがなカードやパズル
- 絵本の音読
- かるた遊び
- お風呂ポスター
- お手紙
しかし、注意しないと良くない姿勢や持ち方・間違った書き順で覚えてしまうリスクもあります。
ただ、それは書字の時の声かけをしたり、幼児むけの筆記具・筆順のわかる教材などを選べばリスクを減らすことができます。



ぜひ、実践してみてくださいね。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!
参考にした文献・Webサイトなど
[2] 齋木久美・市原陽子(2007)「幼稚園の文字指導における理論と背景―小学校への接続を踏まえて―」『茨城大学教育学部紀要(教育科学)』56、pp23-34
[3] 岡本明博(2016)「幼児期における文字の書き指導に関する一考察−長崎市の幼稚園への実態調査に基づいて−」『未来の保育と教育 ー東京未来大学保育・教職センター紀要―』3、pp. 29−36